No。074
新プロダクトライフサイクルの提案
2001.9.10
読者アンケートで、「マーケターなら、もっとよく調べてから書け」とか、「ネタ探しに苦労されているんですね・・・」という手厳しいご意見を賜りましたので、今回は大マジに、私からの提案です。
---
「プロダクトライフサイクル」はご存知でしょうか。
これ、発端は生物学の「誕生-成長-成熟-衰退モデル」から考えられたみたいです(ハハハ、ちゃんと調べたで〜)。
で、ポイントとしては、次のようなものです。
・製品には寿命があるということ
・売上高はある限度に至るまではS字曲線に従い、それ以降は減少する
・導入期、成長期、成熟期、衰退期に区分される
・導入期から成熟期に至るに従って利益率は上昇し、衰退期に入ると低下する。
参考)Philip Kotler /Gary Armstrong『マーケティング原理』
かなり使い古された理論ですが、今でも間違っているわけではないでしょう。
でも、実際にマーケティングの現場に携わっていると、世の中の大半の製品は、「導入期」から、あっという間に「衰退期」に入っています。
いや、「大半」なんて生やさしい言葉ではなく、「99%」といっても差し支えないくらいの製品が、これにあてはまるでしょう。
要は、世の中の「ヒット商品」と言われるもの以外は、すべて「導入→衰退」する商品だと。
だから、このPLC理論も、間違いではないんですけど、あんまり使えないんですよね。
---
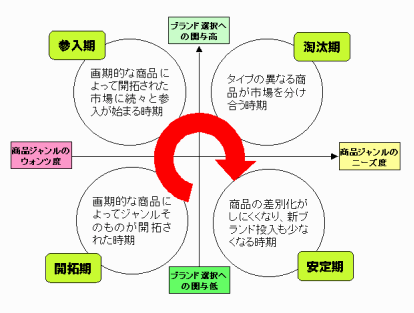
ということで、このような「製品」や「商品」「サービス」の進化を考えるために、私がひねり出しましたのが、右の「新プロダクトライフサイクル」がこれです。
まあ「プロダクト」というよりも、「製品ジャンル」のライフサイクルという感じなのですが・・・。
考え方の基本としては、「画期的な商品」は、新しい商品ジャンルを作り出すということです。
「ウォークマン」や「カップヌードル」なんてもので考えれば、わかりやすいでしょう。
ただ、何も最近のこのような商品・サービスではなくとも、例えば、今では誰も画期的とは思っていない「歯磨き」とか「洗剤」なんてものも、最初は必ずここでいう「開拓期」から始まるということです。
で、しばらくして、その商品が作った市場が「おいしい市場」と見るや、あれこれ「モノマネ商品(サービス)」が参入してくる期が始まります(乱入というべきか?)。
「ウォーキー」って商品知ってます?
たしか東芝でしたね、ウォークマンのモノマネ商品でした。
まあ、東芝の例を出すまでもなく、この「参入期」には、訴訟ギリギリと思われる商品が、やたらと出る時期です。
そういえば、ユニクロが開拓した市場を、スーパーがてらいもなくマネしているのも、この状況でしょうか。
ダイエーは実際に訴えられていますけど、ね。
で、さらにしばらくすると、消費者サイドでも、これらの乱立した商品の選別をする。
そう、商品の「淘汰」が始まる「淘汰期」です。
消費者も、「選別をする」という積極的な選択ではなく、単に「私はこれを買う」という集合体の結果による「選別」なのでしょうが、こうなると、中途半端な商品はすべて排除されます。
ビール会社だって、まともに生きていられるのは上位2社。
自動車業界だって、トヨタとホンダだけ。
淘汰の末には、だいたい、市場を二分する勢力にまとめられます。
それも、タイプの異なった商品を出す2強に集約されると考えてよいでしょう。
(ちなみに、銀行業界も4強になったようですが、結局、勝ち残れるのは2強だけでしょうね)
で、淘汰の末に待っているのが、「安定期」。
安定とはいいますが、気をつけなくてはならないのは、マーケットは安定していますが、「成長は止まっている(だろう)」ということ。
そう、PLCでいえば「衰退期」に近いところです。
ただ、今の世の中で、自分が担当する商品を、手をこまぬいて「衰退」させたら、そいつは間違いなく「クビ」ですね。
だから、「衰退期」という考え方は、現実に即していないと思います。
企業は、自社商品に「永遠なる成長」を期待します。
だから、商品に、何らかの新機軸を付加することを求められたりもすることでしょう。
で、その新機軸の結果が・・・、また「開拓期」に戻るということにもなります。
---
 この「新プロダクトライフサイクル」のミソは、どの「期」にいても、そのジャンルに画期的な商品が発売されると、「ステージ」が変わり、また「開拓期」から始まるということです。
この「新プロダクトライフサイクル」のミソは、どの「期」にいても、そのジャンルに画期的な商品が発売されると、「ステージ」が変わり、また「開拓期」から始まるということです。
例えば、「証券業界」も、大手4社が3社になったりしながら、何とかやっていたところに、突然「ネット証券」という画期的サービスが出現した。
そして、それまでの「証券サービス」というステージから、「インターネットを用いた証券サービス」というステージへと移った。
図で表しますと、こんな感じなのでしょうか。
ちょっとパワポでは書きにくいんですけど、イメージはご理解いただければ、ありがたいです。
例えば、「ビール」というステージは、ラガーの時代やら、スーパードライの時代があって、混沌としていたところに、サントリーが「スーパーホップス」を出して、新たに「低価格」という(ビール業界にしては超画期的な)新機軸を出してきた。
こうなると、新たに「発泡酒」というステージが始まるわけです。
(ちなみに、今は「淘汰期」か?)
ステージがスパイラル的に進化しますので、「プロダクトライフスパイラル」という感じかも知れません。
ただ、ご留意いただきたいのは、「ステージ」は進化しても、実は、その手前の「ビール類」という幅広いジャンルで見れば、「発泡酒」も、「参入期」にある一商品にすぎないのかも知れないということ。
さらに言えば、「アルコール類」というステージで見たら、さらに別な「期」にあるともいえるでしょう。
このように、この新プロダクトライフサイクルは、その商品ジャンルの捉え方によって、その商品のいる「期」が変わってくるということです。
---
いかがでしょうか。
どうか、皆さんが携わっている商品や、身の回りにある商品を、このサイクルにあてはめて考えてみてください。
まだ自分の中でもあまり整理し切れていず、うまく文章では説明しにくくて、申し訳ないのです。
「もっとこうなんじゃないか?」などのご意見があれば、是非お寄せいただければありがたいです。(mailto:tmt@horae.dti.ne.jp)


この「新プロダクトライフサイクル」のミソは、どの「期」にいても、そのジャンルに画期的な商品が発売されると、「ステージ」が変わり、また「開拓期」から始まるということです。